- 風雷益(ふやす/公益)
- 益。利有攸往。利渉大川。
- 彖曰。益損上益下。民説无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利渉大川。木道乃行。益動自巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。
- 象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。
- 初九。利用爲大作。元吉。无咎。 象曰。元吉无咎。下不厚事也。
- 六二。或益之。十朋之龜弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。 象曰。或益之。自外來也。
- 六三。益之。用凶事无咎。有孚中行。告公用圭。 象曰。益用凶事。固有之也。
- 六四。中行。告公從。利用爲依遷國。 象曰。告公從。以益志也。
- 九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我徳。 象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我徳。大得志也。
- 上九。莫益之。或撃之。立心勿恒。凶。 象曰。莫益之。偏辭也。或撃之。自外來也。
- 益。利有攸往。利渉大川。
風雷益(ふやす/公益)
profit:利益/increase:増加,増大,増進
天機まさに来る。乗ずべし。
私利私欲に走るべからず。
損而不已必益。故受之以益。
損らして已まざれば、必ず益す。故にこれを受くるに益を以てす。

いつまでも損じてばかりいれば、油断していた気持も引き締まり、結果必ず益して増しふやすようになる。益は、物がふえること。物をふやすこと。益の字は、皿の上に、横になった水の字があり、皿の上に水を入れる形を表している。皿の中に水を注いで、増しふやしてゆく形。
41山澤損の場合とは逆に、上を損して下を益やすこと、上に立つ者が広く人びとを潤すことである。積極的に困難を克服して、広く社会的利益をはかる者には大吉の卦である。
動けば利を見ると云うか、何事もとんとん拍子に流れのままに有利に事を運んでくれるとき。四方八方からカネが降って湧いてくると云えば大げさだが、何かそれに似た感じで、思わぬところからカネが転がり込んでくるとか、金儲けというより趣味程度で始めたことが当たって面白い程儲かるとか云ったことが起こって来る。
金銭に限らず何事も順調にスムーズに行くときで、運勢は上々吉。
何をやっても上手く行くし、成功の可能性は大きいが、運が良いからと云って何でもかでも手を出して出鱈目のことはしないよう、欲も程ほどに。中庸の道を心する。
折角の好機はそうざらにないから、よく現状を踏まえて有効に行動を起こすこと。
[嶋謙州]
益というものは、損すなわち克己的精神、克己的生活という過程を経て、初めて得る自由をいいます。
ex.,貝原益軒(1630~1714)の初号は損軒であった。八十四歳で亡くなる1年か2年前に初めて益軒に改めた。
若いときはなかなかの道楽者であったが、これではいけないと中年から勉強を始め、忿りを懲らして欲を窒ぐ生活をした人である。
易は損の卦が先であります。自分であくまでも克己努力をして、それから自由を得る。
これが益であります。
[安岡正篤]
益。利有攸往。利渉大川。
益は往くところあるに利あり。大川を渉るに利あり。
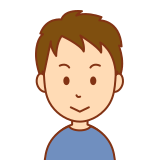
この卦䷩は、否䷋の上の上卦の一陽爻(九四)を損して、下卦に益した形である。
卦の意味が損と反対であるように、卦の形も損を上下反対にした形である。益とは増益の意味。益し加えることで、減らして少なくする損とはすべて正反対の象。
上を損して下に益す、支配者の富を損して民に益すから益という。六二と九五と、ともに「中正」で相い応じているから、往くところあるに利あり。それに下卦の震☳は動くの徳がある点でも、往くところあるに利あり。
上卦巽☴は木である。下卦震は動く、動く木は舟の象がある。そこで、大川を渉るに利ありという。占ってこの卦が出れば、富が増す。どこかへ行く、つまり積極的に進むがよい。大川を渉る、すなわち冒険をするのもよかろう。
彖曰。益損上益下。民説无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利渉大川。木道乃行。益動自巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。
彖に曰く、益は、上を損して下に益す、民説ぶこと疆りなし。上よりして下に下る、その道大いに光る。往くところあるに利あるは、中正にして慶びあればなり。大川を渉るに利あるは、木の道乃ち行らるるなり。益は動いて巽なり、日に進むこと疆りなし。天施し地生ず、益すこと方なし。凡そ益の道、時と偕に行なわる。
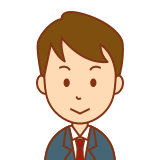
『説』は悦と同じ。『疆』は田の境、无疆で無限の意味になる。『光』は顕。広と解しても通ずる。『方』は所、『无方』は無際限。
益は上から損して下に益す意味、そうすれば下の民の悦びは限りない。䷋の上掛から一陽が下卦に下った、つまり上の君がへりくだって、下の民の富を益してやる、その道義は大いに輝かしい。
風雷益の卦は山沢損の卦と『損益』で一対になり、経済の基本ともいうべき循環の法則を学ぶことができる。山沢損の卦は、民が質素倹約して国益をもたらす。これに対して風雷益の卦は、国が民を助けて富ませようとする。民は喜び、その結果、国も民も限りなく利益を生ずる。「能く損すれば即ち益す」という言葉があるように利益を還元しない国家、会社組織はいずれ倒れることになる。
時や状況に対して従順かつ積極的に行動すれば益をもたらし、日々限りなく物事は進む。天地が万物を生ずるように、遍く益すこと。ただし、益す一方ではない。益の道は損の道と一対になって循環するから、時に応じて損と益を考えて行動すべきである。
卦辞に『往くところあるに利あり』というのは、九五の「中正」に六二の「中正」が「応」じるというめでたい形であるから、往けばおのずから福(=慶)があること。
大川を渉るに利ありとは、上卦が☴木、下卦が☳動、木を行る形。木には水に浮かぶはたらき(=木道)があるが、ここに至って(=乃)その木が推し行られる(=行)。つまり舟である。
舟があれば大川を渉るのに有利である。益䷩の内外卦の徳でいえば、動く☳と巽う☴。理に異って動くときは、その益は日に進むこと限りない。
䷋の九四と初六が入れ換わ占ってこの卦になったということは、天☰が下卦に一陽を施し、その代りに地☷が上卦に一陰を生ぜしめたことである。
天が施し地が生めば、万物の増益すること際限がない。すべて物を益し、他人に益すという道は、天地が季節に応じて万物を益すように、然るべき時機に応じて行なわれねばならない。
象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。
象に曰く、風雷あるは益なり。君子以て善を見ては遷り、過ちあれば改む。
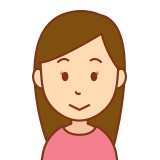
風☴と雷☳とでこの卦になる。風が烈しければ雷の響きはより強くなり、雷の鳴るときは風が疾くなる。風と雷と助け合って勢いを益すから益と名付けた。
君子はこの卦に象どって、他人に自分に優る善さがあれば、直ちにそれに従い、自分に過ちがあれば憚ることなく改める。自分を益する最も大きな道であり、他人にも利益になる。風と雷と相い益するのに似ている。他人の善を見ては、風のように速やかに遷り、自分の過ちを改めるには、雷のように果断であれ。
激しく吹く風と轟く雷。これに倣って、人の善い所を見たら風のように速やかに移り学び、自分に過失があったなら、雷のように決行して改めよ。それは自分だけの益に止まらず、他人にも益をもたらすことになる。
初九。利用爲大作。元吉。无咎。 象曰。元吉无咎。下不厚事也。
初九は、用て大作を為すに利あり。元吉にして、咎なし。
象に曰く、元吉にして咎なきは、下厚事をせざればなり。
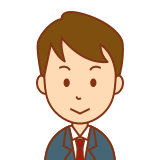
『大作』は大きなしごと。益されて裕かなこと。象伝の『厚事』は、爻辞の大作を解釈したもの。重大な事。
初九は卦の最下位で、本来大きなしごとをする立場ではない。だが今は上を損し下を益す時である。上からの益を受ける立場に初九はおる。それに対して報いねばならぬ。
そこで、この爻を得た場合、大仕事をするのによい。ただし元吉にして咎なし。元吉が答の前提条件。その仕事が完全に善きもの(=元吉)である場合にのみ、咎なしにすむ。少しでも善くないところがあれば、咎を免れない。なぜなら下位の者はもともと厚事重大な事に耐えないのであるから。
六二。或益之。十朋之龜弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。 象曰。或益之。自外來也。
六二は、或いはこれを益す。十朋の亀も違う克わず。永貞なれば吉なり。王用て帝に享す、吉。
象に曰く、或いはこれを益す、外より来るなり。
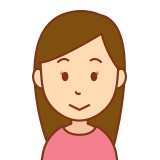
『或益之。十朋之龜弗克違』の句は、損六五にも見えた。益は損をひっくりかえした卦だから、損六五のシチュエーションが益六二に当たる。すなわち下を益す卦で、下にいるから益される立場。国家や会社組織でも、上が利益を独占せず、下位の正しい場所に還元するならば、全体が大きな利益を得る。それは十朋の亀で占っても間違いのない保証された益である。やる気ある人を救い上げて事業を起こさせれば、経済が循環し、社会全体の利益につながっていくのである。
陰爻だから、柔順で虚心。誰彼となく自分を益してくれるであろうこと、貴い亀の甲で卜しても、外れはしない。ただ柔爻で柔位、柔弱に過ぎて、正しい道を守りおおせないことを恐れる。故に占者を戒める意味で、永く貞しければ吉という。
『王用て帝に享す吉』用はこの爻を以ての意、帝は上帝、天帝が原義、『享』は祭る。朱子はこの句を、古代の王者が実際に天を祭ることを占って吉を得た時の判断辞であろうという。されば王者が占ってこの爻を得れば、天の祭りをするのによい。
象伝、外より来るは、損六五の象伝、上(=天)より祐くと同様、益を自分から求めないのに、外からひとりでにやって来る意味。
六三。益之。用凶事无咎。有孚中行。告公用圭。 象曰。益用凶事。固有之也。
六三は、これに益す。凶事に用うるに咎なし。中行に孚あり。公に告ぐるに圭を用てす。
象に曰く、益の凶事に用うるは、固よりこれ有るなり。
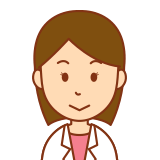
損の六四は、損するのに疾いをもってしたが、同じような意味合いで、この益の六三は益するのに凶事を用いるのである。凶というのは、地の欠けたところ(凵)に交々(メ)陥る象だと説いておるが、この爻は互体の坤の真ん中に居て、変ずれば坎(陥る)として凶の象があるのである。もともと三の位は危地である所に、この爻が内卦の震の極にあって妄動しやすい。その危うさを改めさせるため、これに凶事の試練を与えるというわけである。
六三は下卦☳の最上位におり、上卦に隣接している。下卦☳は動であるから六三は自分から進んで上の六四に、自分に益してくれと乞う(=益之)。自分から益を求めることは君子として恥ずべきことであるが、凶事の場合にそうすること、咎はない筈(=用凶事无咎)。
ただし咎なきためには条件が二つある。第一に中行に孚あり、つまり中庸の道に叶っていること。次ぎには、公に告ぐるに圭を用てす、公は公爵、六四を指す。五の王位のすぐ下だから。六三が隣国六四に、自国の凶事を告げて利益を乞うに当たり、圭玉を引出物にしている。相手に誠信であれという戒めである。前の中行に孚ありと、全く別のことではない。孚に信の意味があるから。
占ってこの爻を得れば、人に物質的援助を求めることもできるが、凶事(葬、災、飢など)の場合以外は求めてはならない。凶事のときだけは求めても咎はない。その際も、中庸の道に違わぬこと、求める相手に嘘をつかないことが条件となる。
象伝の意味は、自分から益を求めるということも、凶事に於ては当然有り得ることだとの意。
六四。中行。告公從。利用爲依遷國。 象曰。告公從。以益志也。
六四は、中行あれば、公に告げて従われん。用て依ることを為し国を遷すに利あり。
象に曰く、公に告げて従わるるは、益するの志しを以てなり。
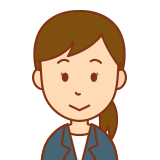
この爻辞は前の六三の爻辞と、意味の上で連続している。公は六四自身を指す。告げに来るのは六三であり、従うのは六四である。
六四は、否䷋から益䷩に変わった際、自分の陽を損して、下卦の初にしてやった、その父である。自己を犠牲にしても下を益してやろうという志が篤い。この公に告げれば必ず肯いてもらえる(=告公従)。
告げるとは、前の六三にあったように、諸侯の国で何かあった場合、王や隣国に報告すること。六三では凶事に限ったが、本来それに限らない。新君の即位、結婚などの吉事も報告の対象であり、それに対して他国から祝いが贈られる。祝いをもらうことも益である。占ってこの爻を得たら、気前のよい援助者があって、願いのままに利益を与えてくれるであろう。ただし、中行あればという条件が附せられる。
この爻は惜しいことに「中」を外れている。そこで、占う人に戒める。中庸の道をふむならば、公に告げて従われん、と。
『用て依ることを為し国を遷すに利あり』~新たに国を遷した場合、近隣の国に依りかからねば立ちゆかない。その依りかかることを依を為すという。
占ってこの爻が出たら、国を遷すのによろしい。用ては、この爻を以ての意。朱子はこの句、昔の人が実際に、国を遷すことを占ったときの良き答えであろう、と。それにしてもなぜ国を遷すということが、この爻に関係するか。清の王夫之は、六四はもと否䷋の初六が遷って来て六四になったのだから遷国という、と。
九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我徳。 象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我徳。大得志也。
九五は、孚ありて恵心あれば、問うことなくして元吉、孚ありて我に徳を恵まん。
象に曰く、孚ありて恵心あり、これを問うなかれ。我が徳を恵む、大いに志しを得るなり。
この爻辞、種々の読み方が可能であるが、一応朱子による。
『恵心』は恵む心。『徳』は得と通ずる。損得の得である。
『矣』は断定の語気を示す。九五は君位にあり、剛毅(陽爻)で「中正」、下にはやはり「中正」なる六二が「応」じている。大いに下々を益することのできる立場にある。
支配者に誠意(=孚)があり、下を恵む心があれば、問わずとも大吉なことは明らかである。そのようであれば、下もまた誠意あって、自分に得を恵んでくれるであろう。
かくて九五は大いに望みのままを得ることになる。占ってこの爻を得た人、他人に恵み
をせよ。他人も自分に恵んでくれて、大吉。
上九。莫益之。或撃之。立心勿恒。凶。 象曰。莫益之。偏辭也。或撃之。自外來也。
上九は、これに益すことなし。或いはこれを撃つ。心を立つること恒なし。凶。
象に曰く、これを益すことなきは、偏辞なればなり。或いはこれを撃つ、外より来るなり。
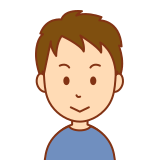
上九は陽剛でもって益すことの窮極におる。鼻っ柱強く、益を人に求めてやまぬ者である。かような者には誰一人益してやろうとは思わない。それどころか憎んでこれを撃つ人もあろう。
孔子が「利に放って行えば怨み多し」というのもそれである(『論語』里仁第四)。
『立心勿恒』は無と同じ、禁止の意味ではない。心を立つは、志を立つと似た用法、心の建て前。占う人、利益ばかりに惹かれて、恒常性のない心の持ち方では、当然凶の結果に至るであろう。
繋辞伝のなかで孔子はこの辞を引いていう、
「危くして以て動けば、民与せず。懼れて以て語ぐれば、民応えず。交わるなくして求むれば、民与えず。これに与するなければ、これを傷る者至る」と。
象伝、『偏辞』は一方だけの勝手な言い分、『荘子』人間世に『巧言偏辞』とあり、ひいて、裁判に於ける片方だけの言い分の意味に用いる。象伝の言うところは、誰も上九に益してやらないのは、益を求める上九の言い分が自分勝手なものだからである。とどのつまり思いがけぬところ(=外)から、打撃がやって来る。



コメント