地火明夷(傷ついた太陽・韜晦すべき時/闇夜・暗君が支配する暗黒の時)
dark:暗闇/a dark night
時に利あらず、退くべし。
力を養い、後日に期すべし。
進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。
進めば必ず傷るるところあり。故にこれを受くるに明夷を以てす。夷とは傷るるなり。
勢いにまかせて進んでゆけば、必ず傷つくことがある。
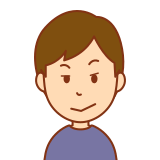
『明』は明るいこと、『夷』は、傷つけられることを指す。明が夷れる、賢明なる者が傷つき害されることである。明るさが害されるのであるから、真っ暗闇の状態。明るい日輪が、地の下に没してしまったのである。地上は暗くなって、夜が訪れたのである。
35.火地晋とは反対に太陽(離☲)が地(坤☷)の下に没し、暗黒が支配している形である。道理が道理として、正論が正論として通じない、理不尽な暗黒の世である。また暗愚な者が上にあって、せっかくの才能ある部下を抑えつけている、と見ることもできる。こんなときに、なまじ才能を発揮して局面打開をはかろうとすれば、たちまち周囲から叩きつぶされることになりかねない。自分の明知と徳を隠して時を待つ。苦難の中で磨かれた実力は、やがて珠玉のごとく輝く。
真っ暗で何も見えない状態を表しており、手さぐりでなければ先に進めない。
おそらく何事も不如意のときで、進んだら失敗することは充分自己で察知することが出来るときであろう。運気は弱く、沈みと停滞ムードで、動けば足をすくわれたりして面白くない。こんな時は無論じっと我慢せねばならぬときで、どんなつらいことや世間から爪弾きされることがあっても絶対に耐えなければならない。
これがこの卦の宿命だが、しかしどんなに暗い夜であっても夜が明けないことはないのだからそれまで待つこと。遅かれ早かれ、きっと好転のきざしが見えて来るときが来る。この時期を決して逃さないこと。
[嶋謙州]
積極的に進歩、行動することは非常に大切なことであるが、同時に非常に警戒を必要とします。そこで易は明夷の卦をおいております。
この卦は地が上、火が下、すなわち火が地の下に入るということは暗くなるということであります。そこで大象は用晦而明―晦を用いて而して明なり、とうまく表現しています。
火地晉で非常に進みますが、どうかするとそれで失敗する。進むという動作は陽の働きでありますから、必ずそれの裏打ちの陰の働きが必要であります。
たとえばこの卦の形からいってもわかりますが、火が地の下に入るわけですから夕暮れ、夜になります。夜になると、昼間の仕事が終わって家に帰る。家に帰って寝てしまっては駄目で、そこで学問をするとか何か芸を楽しむとかしなければなりません。これが明夷であります。夷は普通「えびす」と読みますが「つね」という意味もあります。元来、大の字の中に弓の字を入れた文字であります。これは弓を張って仁王立ちになっておるという文字であります。
中国人~中華人は、自分を中華と称して自尊心をもっております。そして北の方を北狄~けものへんに火という字を使い、南の方は南蛮、これはこれは虫という字を使っております。また、西のほうは、この二つよりややよいとされる西戎、これはチベットとかトルコとかウルグアイという地域です。この地方の住民は、馬に乗ること、弓を射ることがたいへん上手でありまして、中華人は歴史的にも随分これに悩まされてきたわけであります。
またこの戎という字は、閧ノ武器を持っておるという字でありますから、いかに西方の異民族から侵略を受けて苦しんだかということがこの文字でもかわります。
ところが東のほうには、一番尊敬する言葉をあてはめ、東夷といいました。これは主として山東地方であります。現在もそうでありますが、中国の地理、歴史を学びますと、中華人は、北狄、南蛮、西戎よりも東夷を一番怖がり、またしたがって尊敬しておりました。
山東人は非常に武勇にすぐれ、斉魯という言葉があるように、斉がその代表でありまして、桓公とか名宰相の管仲などがでました。
我が国の荻生徂徠が東夷徂徠と称したというので、漢学者は皆中国を崇拝して日本を軽蔑する、と文句をいいますが、これは間違いで、徂徠は自慢で東夷といっておるのであります。
中国人は文の民で武に弱い。ところが山東人は皆武勇であり、立派である。日本も中国から東に位置して、武勇の国民である。
そこで徂徠は自ら東夷と称して文弱の民にあらず当方武勇の民であるという自慢の言葉であります。それをよく説明しないものですから誤解され、攻撃されておりますが、徂徠にとってははなはだ迷惑なことであります。ちょっと皮肉な人ですから、そういわれると恐らく「こいつ無学だなあ」と思って笑うだろうと思います。夷という字はこのように武勇を表す文字で敵を平らげるという意味があります。したがって平和という意味もあります。昼働いて、夜になるとあかりをつけて勉強をする、これが本当の明夷の意味であります。
[安岡正篤]
明夷。利艱貞。
明夷は、艱貞に利あり。
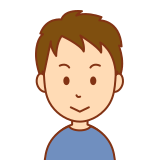
火地晋を反対にしたのがこの卦。『夷』は傷痍の痍と同じ、傷つく、やぶる。この卦は坤の地の下に、離の日輪が没した象を取ったものである。『夷』の字は、大と弓を重ね合わせたもの。大弓は物を傷つけ破るので明るさを破る=闇と同じである。太陽の明るさが傷つけられるという意味で明夷(明やぶる)と名付ける。
この卦の主体は六五であるが、そのすぐ上の上六が暗君で、五の立場は極めて困難である。そこでこの卦を得たときの判断として、艱貞に利あり、艱難を自覚して、苦しみつつ正道を守るときにのみ利益があるという。韜晦して身を守るがよい。
彖曰。明入地中明夷。内文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。内難而能正其志。箕子以之。
彖に曰く、明地中に入るは明夷なり。内文明にして外柔順、以て大難を蒙る。文王これを以てす。艱貞に利ありとは、その明を晦くするなり。内難あって能くその志しを正す、箕子これを以てす。
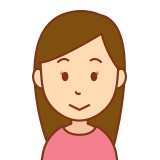
『蒙』は遭う。また冒と同じで危険を冒す。明☲が地☷の中に入るので明夷という。卦の徳でいえば、内卦☲は文明、外卦☷は柔順。人間でいえば、内心叡智に富み、他人に柔順な人。周の文王(前十二世紀)はまさにそのような人であった。明智を隠して暴君の紂王に従順に仕え、羑里に囚えられるというひどい難儀を蒙むりながら身を全うした。卦辞に貞に利ありというのは、自分明智を包み隠すがよいということ。内難とは暴君の身内であり、その国内におるという難儀。
箕子は紂王の異母兄、狂人のふりをして、その智慧を隠し、正しい志を守り通した。文王、箕子とも六五にかけてある。紂が上六に当たる。五は上に近いので内難という。
象曰。明入地中明夷。君子以莅衆。用晦而明。
象に曰く、明地中に入るは明夷なり。君子以て衆に莅むに、晦きを用てして而も明らかなり。
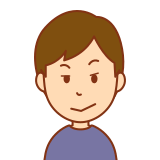
『莅(蒞)』は臨む。君子の智慧は太陽のようにすみずみまで照らしうるが、あまりにこまかいところまで気がつき過ぎては、寛容の徳と矛盾する。そこで君子は地中に隠れる太陽の卦形に法とって、民衆に臨む場合に、わざとその智慧を晦まし、茫漠とした態度で接する。そうすれば相手は心許して、本心すべて君子に看破される。晦を用て臨むことが逆に、真の明察になるのである。
小さな明察を戒める語として、『老子』に「その政、察々たれば、その民は缺々たり」とある。王者の冠、前に玉すだれが、耳の辺に綿玉がぶら下っているのは、過度の聡明を自ら抑制するためである。
初九。明夷于飛。埀其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。 象曰。君子于行。義不食也。
初九は、明夷于きて飛んで、その翼を垂る。君子于き行く、三日食わず。往くところあれば、主人言うことあり。
象に曰く、君子于き行く、義食わざるなり。
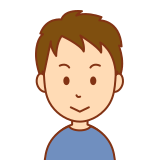
『于』は、ここに、またはゆくと訓する。『主人』は宿を借りた家の主人。言はいわゆる物言い。
この卦は傷つく意味である。初九も傷つくことを免れない。しかし、卦の初めだから傷も浅い。この危険な国を飛び去ることはできる。~明夷于き飛ぶ~初九は☲明の一部、それが傷つくので明夷といった。ただ傷ついた翼は、ともすれば下に垂れそうになるが。
君子以下は占断のことば。この爻を得た人は、旅に出て、三日も飯が食えないだろうし、どこかに泊めてもらおうとすれば、その家の主人怪しんで文句を言うであろう。ということは、世に容れられず、彷徨しても禄にありつけない。誰かに仕えようとしても、その君主は、お前の理想は現実に合わないといって、非難するであろう。もっとも世の中の方が狂っているので、義としてその禄を食うべきでない。
六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯。吉。 象曰。六二之吉。順以則也。
六二は、明夷、左の股を夷る。用て拯う馬壮んなれば、吉なり。
象に曰く、六二の吉なるは、順にして以て則あればなり。

明夷の時、傷つかずにはすまない。左の股に傷ついた。歩くのに不自由であるが、利き足の右でないだけにまだましである。強壮な馬でもって救ってもらえば、なおこの大難の世界から逃げのびることができよう。
二は初より一段進んでいるだけに傷が深い。初ではまだ飛び立てた。二は歩くことすら困難になっている。
占ってこの爻を得れば、ひどく傷ついて難儀にかかるが、迅速に収拾すれば、なお吉を得ることができる。なぜなら、六二は陰、柔順であり、「中正」(内卦の中、陰爻陰位)という、法則にかなったところがあるからである。
九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。 象曰。南狩之。志乃大得也。
九三は、明夷、南に于きて狩し、その大首を得。疾く貞すべからず。
象に曰く、南にこれを狩る、志し乃ち大いに得るなり。
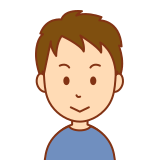
『大首』は巨魁の意味。『疾』は速。
九三は剛爻が剛位におる。至ってなるもの。下卦☲明の最上爻だから、最も明智がある。それだのに、☷という陰ばかりの至って暗い闇の下にある。しかも上六という暗愚な君と「応」じている。
最初はその明智を隠して忍耐しているが(=明夷)、いつまでもそうしていられない。離火の威武を用いることを南狩に象る(離を南・兵戈とし、変じた震を進撃とする)南に向かって征討の軍を起すに至る(=于南狩)。南は明るさに向かう方角。中国の方向感覚だと南が上で北が下。
九三は世を明るくしようと、上の方へ攻めるので南という。狩というのは、狩猟にことよせて兵を挙げること。明らかなものが暗いものを討つのである。
悪の巨魁(上六)を討ちとることは必至である。(=得其大首)。
ただしこれは革命である。非常のことである。軽軽しくしてはいけない。いかに明夷の因をなしているとは言え、下から上を討つというのでは、そうやすやすと事を挙げてはならない。正しくないものを正すのだからと言っても、すぐに行って良いというものではない。
どうしても彼を取り除かなくてはならないという勢いが天下の声となり、やむにやまれずして行われた時にのみ、初めて天下の志を達することができるのである。
明夷の闇の因となっている支配者は本当の君主(五爻)ではなく、その上位に置かれ、やがてはその位を保ち得ないことが示されている。だから下より上を討つにしても、決して臣が君を奪うものではないという道筋が整えられている。
故に作者は疾く貞すべからずという占断辞でもって占者を戒める。
悪を正すのに急速であってはならない。殷の湯王も、周の文王も、桀や紂の暴君に幽閉されて随分と辛抱した上での革命であった。小事を占ってこの交を得た場合も、同様、正しいことをするにしても急であってはならぬと占断する。
象伝の言うところは、南に巨魁を討ち、ここで始めて(=乃)太陽を取りもどす志が大いに満足させられる。
六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。 象曰。入于左腹。獲心意也。
六四は、左の腹に入る。明夷の心を獲たり。于きて門庭を出ず。
象に曰く、左の腹に入るは、心意を獲るなり。
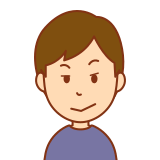
『左腹』の左は、へりくだる感じ。右が尊いから。『腹』は腹心の意味。左腹に入るは、へりくだって相手の心にもぐりこむ。ということはその気持ちをつかむ。明夷の心を獲たり、はその意味である。明夷はこの場合、明を夷る暗君を指す。相手の気持ちをつかんでいるから、暴君に近いけれども、危険はない。
左腹に入ってどうするのかと言えば、頭と共謀するのではなく、むしろその中心を知り尽くす事によって、その不正の仲間となることを欲しない。
また傷害が、やがては己の身にも及ぶであろうと察し、逃れて遠ざかるのである。
暗君の難を避けようと、自分の門内、庭園に隠れれば、却って相手の気に逆らう。于きて門を出て、その朝廷の中に於て、避難するのが賢明である。大隠は朝市に隠るの意である。占ってこの爻を得たら、このように心掛けるべきである。
象伝は、左腹に入るの句と、明夷の心を獲と同義であることを説明する。心を心意と布衍したのは、上に腹の字があり、心が心臓の意味と取られる惧れがあるからであろう。
六五。箕子之明夷。利貞。 象曰。箕子之貞。明不可息也。
六五は、箕子の明夷る。貞しきに利あり。
象に曰く、箕子の貞、明息むべからざるなり。
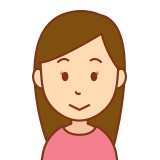
箕子は初め紂王を諌めたが聴き入れられない。人は亡命をすすめたが、かれは「人の臣として、諫めて聴かれないからといって去るのは、君の悪を暴露することで、人民の前に良い子になることだ。自分はようしない」といって、髪をふりみだし、狂人のまねをして、奴隷に身を落した。箕子の明夷るとは、箕子が自分の明智をわざと夷り、韜晦したこと。
上卦☷は陰が重なり、五はその真ん中、最も暗黒なる場所、上六という暗君に近接して、しかも貞しさを失わない。箕子に似ているから、かく言う。貞しきに利ありは、占う人への戒め。暗黒時代にあり、暴虐な支配者の下にあっても、貞しさを固守すべきである。象伝の意味、箕子の爻に対して利貞という徳を与えてあるのは、自らその明を晦ましながらも、その明がついに消えることがなかったからである。韜晦に狎れて明が本当に消えたのでは貞とはいえない。
上六。不明晦。初登于天。後入于地。 象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。
上六は、不明にして晦し。初めは天に登り、後には地に入る。
象に曰く、初めは天に登る、四国を照らすなり。後には地に入る、則を失うなり。
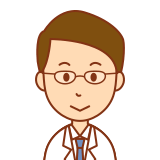
他の爻辞辞みな明夷の語を含む。これだけに無いが、明の夷れた意味は見られる。
二爻を文王にあて五爻を箕子に喩えるならば、この上爻は明夷の昏昧を作った頭で、紂王に見立てることができる。
陰爻でしかも☷の一番上におる。陰爻ばかりで暗い、純陰坤の極まるところにいて、自らの暗愚を覚らず、力にのみ頼る。徳が不明で、本当に晦い者である。とにかく卦の最上位にあるので、初めは天に登るばかりの高位~四方の国を照らすべき高位にあるが、人の明を夷るようなことばかりするので、やがて日は西方へ没するがごとくついには自分を売って、革命の旗の下に命を落とし、地に埋められる。道(=則)を失ったからである。



コメント