澤山咸(感応・夫婦の道/感受性)
sympathy:共鳴共感/influence:感化
希望達成の時期なり。
多情は禁物、一意専心事に当たるべし。
有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮儀有所錯。
天地ありて然る後万物あり。万物ありて然る後男女あり。男女ありて然る後夫婦あり。夫婦ありて然る後父子あり。父子ありて然る後君臣あり。君臣ありて然る後上下あり。上下ありて然る後礼儀錯くところあり。
この卦が易経下巻の最初に置かれる理由を、序卦伝は、男女があって夫婦があり、夫婦があって然る後、父子君臣上下の人倫が発生するという。上巻が万物の創始者である天地(=乾坤)に始まったに対し、下巻は人倫の発端である男女をもって始めるのだということ。
咸とは無心の感。感応すること。心のふれあいなくしては人間の社会生活はなりたたない。その社会生活の最小単位、心の典型、それが夫婦である。ここから夫婦の道の始まる卦としている。感ずるということは若い男女ほど顕著なことはない。兌☱は若い女、艮☶は若い男を表し、もっとも感応しやすいところからこの卦によって感応の原理を示す。
咸の原理は夫婦から社会一般、さらには天地宇宙にまで敷衍することができる。
『咸』は『感』の古字。祝詞を収めた器の口を誠で封じて、神の感応を待つところから、感通・感動・感覚・感化・感触・感和の意味が生じた。
咸とは感応することである。物事を見て感応するには心を要す。また感応は二心がないところに生じるものである。感じ方が正しくないと、感情が乱れ、心が泡立つ。大波が立ち、揺れる場合もある。そうなると物事ははっきり見えてこない。物事を真に心で感じ、受け止めた時は、まさに『明鏡止水』である。一瞬にして、心の目で物事の真相をはっきりと見透すことができる。
[易経一日一言/竹村亞希子]
感情や心の動きがまともに現れるとき。物事を肌で感じ、情愛的な面で処理していくのが適当といえる。運勢は弱くないが、そうかといって手放しで喜ぶ状態ではなく、未だに何分にも上向きになりかけた時だから物事は慎重に運ぶよう心掛けること。
何事も感情に動いて誤る傾向があり、何の考えや知識も持たず飛びついて失敗する恐れもあるから充分きつく戒めておく。
事前に理性を動かし、徐々に行動して成果を上げるようにすることが大切。
感情の赴くまま惰性に流れがちなので、常に第三者の意見を尊重して行きたいものである。
恋愛関係は特に発生しやすく、人との交際も多くなる。
[嶋謙州]
咸とは感と同義で、心のふれあいであります。感銘、感受、感応の感であります。
我々の生活行動というものは、複雑な感覚、感応からはじまる。
そこで咸の互卦~ニ爻、三爻、四爻、五爻をみますと、下が風☴で上が天☰~天風姤であります。つまり咸の卦は天風姤の互卦をもっておるのであります。
姤は、あう、ゆきあうという文字でありますから、陰陽、男女が相感応することで、従って澤山咸の卦は夫婦の始まりであります。恋愛もこの卦であります。
[安岡正篤]
咸。亨。利貞。取女吉。
咸は、亨る。貞しきに利あり。女を取るときは吉なり。
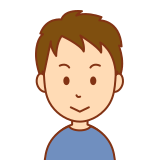
『咸』は感の意味、男女が互いに感応することである。なぜ咸といって、感といわないか。宋の王応麟によれば、咸は無心の感である。感の字の心を除けば咸の字になる(『困学紀聞』。清の王夫之も同説)。
また程氏によれば、咸には皆の意味がある。感応ということ、男女の間、ことに若い男女に於て鋭敏であるが、広く見れば、万物みな感応しないものはない。で、皆と感との両義を含ませて、咸の字を用いたという。
咸とは、感ずるという意味だが、それは心に感ずるばかりでなく、手や足に物の触れたのを感じるような感覚的な感じ方も含め咸という。
また、咸は、「みな」とか「ことごとく」と訓読みするように、目に触れれば目に感じるし、胸に思えば胸に感じる、隅々にまで行き渡っている人間の感性、感覚のことを言っている。
また、人間の感性ばかりでなく、水蒸気が冷気に感応して雨となったり、斜陽を色に感じて空が夕映えするような、自然界における感応作用も咸とみなしている。
人間同士の感応を考えてみれば、やはり若い男女の異性に対する精神的、肉体的な感性を挙げなくてはならない。
下卦の艮は少い男、上卦の兌は少い女である。尊い筈の男のほうが女にへりくだっている。これが実は男女相い感応し、結婚する正しい道。婚礼の当日、花婿が馬車で花嫁を迎えにゆき、助け乗せて、自分で馭者を勤める作法があるのも、その意味である。
また艮には止まるの意味がある。下手に動かず、じっとしていることで、そのまごころが一層相手を感動させる。兌には説ぶの意がある。下卦のまごころに説んで応ずる。その意味でも、この卦に感の意味が生ずる。
感応しあうという意味の卦であるから、占ってこの卦が出たら、願いごとは必ず亨る。ただし動機が貞しいことを条件とする。貞しくなければ、願いごと亨らぬばかりか、することなすことすべて凶になるであろう。また男女相い感ずる卦だから、この卦を得た人、嫁を取れば、結果は吉。
彖曰。咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可見矣。
彖に曰く、咸は感なり。柔上にして剛下なり。二気感応して以て相い与す。止まって説ぶ。男女に下る。ここを以て亨る。貞しきに利あり、女を取るときは吉なり。天地感して万物化生す。聖人人心を感して、天下和平なり。その感するところを観て、天地万物の情見るべし。
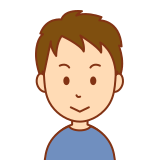
咸は感なりとは、同音の字で卦名を解説したもの、上巻にも多く例がある。柔上而剛下の句、朱子は基本的には、上卦の兌は陰卦、下卦の艮は陽卦だから、柔(陰卦)が上におり、剛(陽卦)が下におる意味だと解するが、そのほか一説として、卦変による解釈をも紹介している。すなわち咸は、旅の六五と上九が入れ換わった卦である。六五の柔が上位に上り、上九の剛爻が五の位に下ることによって咸になったことをいう、と。この場合、柔上而剛下の旬は、柔上って剛下ると読む。いずれにしても、陰と陽が感応する形の卦である。前説でゆけば、陰卦が上にあり、陽卦が下にへりくだることで、後説でゆけば、陰が上り、陽が下ることで、陰陽の二気が感応して、和合~相い与す~する。「二気」とは陰と陽の気。二気が交感して万物は形成される。恋愛、結婚も二気の交感である。もともと質が違い、反発し合う二気であればこそ、感応し合い、相与するのである。
下卦艮には止まるの徳が上卦兌には説ぶの徳がある。また下卦の象は少男、上卦の象は少女で、男が女にへりくだる形になっている。徳からいっても象からいっても感応の意味になる。そこで、この卦の判断辞として、亨る、貞しきに利あり、女を取るときは吉、という。
赤の他人だった少い男女が一目で相い感応して、それから終身結ばれることがあるのは、自然の神秘な働きである。天と地との二つの気(陽と陰)が交感することでもって、万物はそれぞれの形をなして発生する。同じように、聖人のまごころが億の人々の心を感動させることでもって、天下は平和になる。天地が交感して万物を生じ、聖人が民心を感ぜしめて平和をもたらす、その感通の道理をよく見れば、天地万物の秘密は、暗黙のうちに見てとることができよう。
感じるということは本能的なことだから、その対象を取捨選択し、良いものだけを感じるわけではない。だから、感じたものの中から受け取って良いものと良くないものとを分別しなくてはならないのである。これを簡潔に言うと「貞に利ろし」ということになる。
感じる作用を感性とするならば、感じたものを識別するのが知性で、この二つは車の両輪のようなものである。
感ずるときには、正しい知性をも共に働かせ、いつも正しいものを感受するようでなくてはならない。男女の例でいえば、若い妻が自分の夫だけを待ち、他の男へは少しも心を向けようとしない。それが本当の咸であり、これを推して「女を取る(娶る)に吉」というのが、彖辞の大意である。
象曰。山上有澤咸。君子以虚受人。
象に曰く、山の上に沢あるは咸なり。君子以て虚にして人を受く。
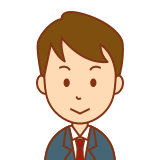
咸の卦は山の上に沢がある。沢は水をたたえて、その水気は下へ下へとしみ通る。この沢が山の上にあるので、当然水気は山に浸透することになる。山は土でできている。土はいつも乾燥していて、その中は空虚なので、沢の水気を十分に受け容れて自分も潤うのである。かくて山と沢の気は感通する。ある人は、この山と沢の感通に象とって、心の中を空にすることで、他人を受け容れる。心の中が空虚ということは、我がないこと。
心にある空虚な隙間をいう。これは心が動く空間であり、感じる能力、感性の源である。人の言葉や心を受け容れるには、いくら知識や経験を積み重ねても、未だ知らないことがあると、虚心坦懐な姿勢で向かうことが大切である。
思い込みで一杯になっていたり、知識だけにとらわれていたら、どんなに素晴らしい出来事や人物に出会っても、受け容れられず、何も感じられない。
先入主が心の中にあっては、人を容れることができない。我がなく、先入主がないことによって、ひろく他人を受容し、他人と通しうるのである。この自分を虚しくするという態度は、老子が処世の道として尊んだところである。老子は、目に見える有の世界の奥に、より高次の実在、無を考える。無は有よりも尊い。だから人間も、さかしくあるよりは、虚心であるべきだというのである。
初六。咸其拇。 象曰。咸其拇。志在外也。
初六は、その拇に咸す。
象に曰く、その拇に咸す、志し外に在るなり。
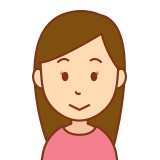
以下の爻辞いずれも、人の意欲に感応する人体の箇所を挙げて、感応の理法の象徴とする。肉体に象徴を求めたのは、これらの文句は問う人への解答であり、相手が自分の身体にひきくらべて悟り易いようにとの意図からである。
『拇』は足の親指である。これを事に当てると物事の始めと見る。拇に咸す、咸は感じ動く。欲する対象と接触するよりも先に、自分の足の親指が、対象の発する電波のようなものを感じ取ってむずむず動くこと。人が動こうとするときは、まず第一に足の先に力を込めるものである。動き出す以上、その心は進もうとしている、外へ向かっている。外というのは、外界に感応していることである。
初六は外卦の九四と、陰陽「応」じている。初六の気持ちは、そちらの方に向かっており、またさればこそ足の親指がむずむず動いたのであるが、何分にも足の親指だけでは全身を動かす力はない。初六が進もうと思っても、まだ進むことはできない。だから吉とも凶とも判断を加えていない。しかし大体において、この卦は感応を説くものの、六爻とも静かにしているのがよく、自分から動こうとするのはよくない。応はあくまで自然で無心であるべきだから。
六二。咸其腓。凶。居吉。 象曰。雖凶。居吉。順不害也。
六二は、その腓を咸す、凶なり。居れば吉。
象に曰く、凶なりと雖も、居れば吉なるは、順うときは害あらざるなり。

『腓』は、こむら、ふくらはぎ。人が歩こうと思うとき、その意志はまっさきにこむらの筋肉に感じ取られ、こむらが先に動いて、足はむしろそれについて動くのである。つまりこむらはせっかちで、自分を守ることのできないもの。六二は、足の親指である初六の上、ちょうどこむらに当たる。それに陰柔の爻であり、自主性のない点でもこむらの性質に似ている。そこで辞に、その腓に咸す~こむらがむずむず動くという。妄動の危険がある。しかし、幸いに六二は「中正」(二は内卦の中、陰爻陰位で正)の徳をもっており、その位置に安んじて居る限りは安全である。占ってこの爻を得た場合、動けば凶、静かにしていれば吉。象伝はさらにことばを添えていう、自分から動いては凶であるが、道に順って妄動しなければ害はない。
九三。咸其股。執其隨。往吝。 象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。
九三は、その股に咸す。執ることそれ随う。往けば吝。
象に曰く、その股に咸す、亦処らざるなり。志し人に随うに在り、執るところ下きなり。
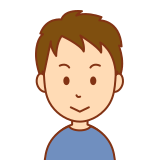
九三は、六二、腓のうえ、股に当たる。股は足に随って動くもの、自主性をもたない。執るとは、主義としてそうすること。下の二、すなわち足の親指とこむらとともに自分で動こうとするも九三、つまり股も、それに釣られて、じっとしておれない。むずむず動く~その股に咸す。
大体、股というのは、その主義として、他に随う方針のみを執るものだからである~執ることそれ随う。初と二は陰柔の小人だから動くのもむりはないが、三は陽剛であり、内卦☶止の極点におる。当然静かに泰然としているべきだのに、このように自立心のない態度は、恥ずかしいことである。
沢山咸は、特『正しきことに感じる』を尊ばなければならないのに、正応の上六とは感応せず、隣の六二に固執して、それとともに感じ動く。六二に『居れば吉』とあったが、この九三も同様に『居れば吉、往けば吝』である。六二に感じ固執するのは下卑ており、恥ずべきである。
占ってこの爻を得た人、いつも他人の後について、進もうとすれば、恥ずかしい思いをせねばならない。独立心を養うべきである。
九四。貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。 象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。
九四は、貞しければ吉にして悔亡ぶ。憧憧として往来すれば、朋爾の思いに従う。
象に曰く、貞しければ吉に悔い亡ぶるは、いまだ害に感せざるなり。憧憧として往来するは、いまだ光大ならざるなり。
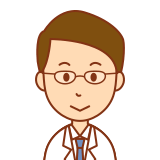
『憧憧往来』は、思いがしきりに行ったり来たりして、心が彷徨うこと。心が安らかでないこと。聖人は別として、多くの場合、自分の好むものを愛して感じ交わるのが普通である。知性ではいけないと分かっていても、思いのままにならず、愛するものところへ走ってゆく。
『朋爾の思いに従う』とは、自分と同じ陽爻(九三と九五)を朋とし、皆それぞれ私情のままに思い感じ迷っているという現実を詠嘆しているのである。
心が迷うのは、私心や私欲に惑わされて、真に物事を受け止めて感ずることができないからである。私心を捨てて感じ入るところがなければ、決して思いは定まらないものである。
九四は、九三の股の上、九五の脢の下である。そして三陽の重なった真ん中にある。ちょうど心(心臓)に相当する。心は肉体のなかで最も感じ易いもの。さればこの爻は咸卦の主体である。
他の五爻みな、その何々に咸すというが、この爻だけ、その心に咸すといわない。けだし心の性質が、他の肉体部分に比べて、とらえどころがないからである。心は外の対象に感じて反応するが、その感応のしかた、正しく且つ持続的でなければならない。異性に対して淫心を、上位者に対して媚びをもって反応するなどは、不正な感応である。
ところが九四は、陽爻で陰位におる。すでに「不正」であり、正を持続することはできない。そこで爻辞は、占断のことばでもって、占者への戒めを与える。心を正しくして、その正しさが持続する(=貞)ならば吉となり、九四の立場としてあるべき筈の悔いも消滅するであろう。もし心定まらず憧々と注きつ戻りつして、正を守りえず、私欲の対象にだけ感応していたのでは、広大な範囲の対象と感通することはできない。せいぜい限られた仲間だけが、その人の気持ちに応じ従うだけであろう。
孔子は、繋辞伝にこの憧々往来、朋爾の思いに従うの旬を引いて、次ぎのように布衍する。
「天下何をか思い何をか慮らん。天下同帰にして殊塗一致にして百慮。天下何をか思い何を慮からん。日往けば月来り、月往けば日来る。日月相い推して明生ず。寒往けば暑来り、暑往けば寒来る。寒暑相い推して歳成る。往くとは屈するなり。来るとは信(=伸)びるなり。屈信相感じて利生ず云々」
右にいう意味は、心のなかにせせこましい私心があってはならない。私心が全くなくなれば、ひろびろとした万物感通の境地が開ける。天地には私心がないから、日が往けば、月がそれに応じてやって来るし、暑さが往けば、それに応じて寒さが来る、その無窮の往来こそ、自然の無心の感応だということである。
象伝の、いまだ害に感せざるなりは、初心がまだ正しくて、みだりに利害に感じないことをいう。
九五。咸其脢。无悔。 象曰。咸其脢。志末也。
九五は、その脢に咸す。悔いなし。
象に曰く、その脢に咸す、志し末なり。
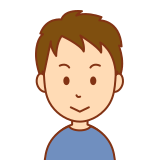
『脢』は背中の肉。心臓より上で、口よりは下にある。四が心臓、上が輔頬舌であるから、九五は背の肉に相当する。ところで背中といえば、心臓の裏側にある。手足や口が心(=心臓)の命令を受けて働くのに対し、背中だけはそっぽを向いている。外からの刺戟に感ずることもない。また背中には目がないから、外の何物かに向かって特に惹かれることもない。脢に咸す~背中の肉に感じがある~人間でということは、つまり最も反応のない、感動のない状態を意味する。
人間でいえば、広く外の世界の人々と感じ合うことのできない、一方また特定の人とプライベートなわずらわしい関係ももたない、孤高独立の状態である。判断として悔いなしという。占う人、外の刺戟に無感動な、孤高、静謐の態度を保つがよい。他人を感化することはできぬまでも、後悔に至ることはないであろう。
象伝、志し末なり。末の字は木の先端の細くなったところ。背中の肉のような、世間にそっぽを向けた処世態度は、安全ではあるが、他人を感動させることがないだけに、その志は末梢的といわざるを得ない。
上六。咸其輔頬舌。 象曰。咸其輔頬舌。滕口説也。
上六は、その輔頬舌に咸す。
象に曰く、その輔頬舌に咸す、口説を滕ぐるなり。

『輔』は唇歯輔車の輔、上あご。『輔頬舌』とは、口舌こと。『滕』は騰と意味が近い。騰は馬がはねあがる、滕は水がわきあがる。輔も頬も舌も、みな人体の最上部に属する。上六は卦の一番上に位置するからこれらの字が用いられる。
また上卦は兌、説卦伝に、兌は説(=悦)言、口舌の象という。舌はもとより、輔も頬も、ものを言うための道具である。上六は咸卦の窮極、また上卦、兌、説言の終りである。人を感動させるのにまごころをもってせず、相手を悦ばすような言語を以てしようと努める。これは小人女子のすること。上六は陰爻、小人であり女子である。輔頬舌に咸すとは、しゃべりたくて、上あご、頬、舌をむずむず動かすさまをいう。陰柔不中で卦の極にあり、感ずることも浅はかで誠実さがない。「口先ばかりで感ずる」といった、本当は感じてもいないことを口先だけで言い繕っているようなもの。
占って、この爻が出たら、凶であるこというまでもない。男子たるもの、このような態度があってはならないのである。象伝の意味は、輔頬舌をむずむず動かすのは、口先だけの弁舌を、湧き出る水のように、勢いよく揮おうとしてである。



コメント