山雷頤(口・養う/養いの道・涵養)
life:生活/nourishment:栄養
言動に注意すべし。急げば争いあり。
内容は空虚なり。時期熟するを待つべし。
物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。
物畜えられて然る後養うべし。故にこれを受くるに頤を以てす。頤とは養うなり。
序卦伝に、物畜れば養わねばならない。故に大畜の次ぎに頤の卦が来るという。
物が十分蓄えられてこそ後養うことができるようになる。
頤は、おとがい。あごのこと。(⇒噬嗑)転じて養う。頤は、養いの道について説く。
中に何も物がはいっていない大きく口を開けている形。
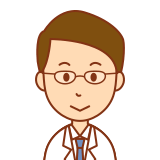
中に物があれば新たに取り入れることができない。新たな養いを受け付けることができない。空虚であることが重要である。私心がない、私利私欲がない、何もないということがポイント。
input:悪食が身体を損なうように、知識も思想も取り入れるときは正しいものでなければならない。
output:口はわざわいのもと~言葉足りず、余計なひとこと、しゃべり過ぎ、舌禍に注意。
病は口より入り禍は口より出ず:言語飲食には特に注意せよ。
この卦がでたら現在何かを求めているときで、それらは職業、結婚の相手、土地、住居、家財道具、衣裳、宝石など生活に密着しているものに多い。
しかし、幸いなことにこの卦の場合、自然と食べることが身についているというか、不思議に生活能力が与えられていることである。
運気も悪くなく、大きな仕事や一生をかけたような仕事をやるだけの強さはないが、日常のことや生活を得るための仕事であれば遠慮なくやってよいといえよう。
また、人間関係というかお互いに最初は多少打ち解けず、相手の心を探りあったり、疑問におもったりするときもあるが、だんだんと付き合って行くうちに自然に解きほぐれて、気心も知れるというか仲良く話し合えるようになっていくから心配いらないとも言える。
[嶋謙州]
頤はあごである。この卦の上卦が上あご、下卦が下あご、また中の四爻が上下の歯とみることができ、養うという意味があります。具体的に何を養うかと申しますと、禍の基となる言語を慎み、健康の基である飲食を節して、自らの徳と身体を養うことであると教えておるのであります。
[安岡正篤]
頤。貞吉。觀頤。自求口實。
頤は、貞しければ吉。頤を観る。自ら口実を求む。
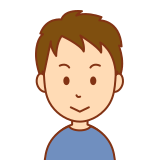
口実とは、口の中に満ちること。口の中に満ちるものには「飲食物」と「言葉」がある。平生何を養っているかをよく見極める、それが正しいものであれば吉。
『自ら口実を求む』とは、まず自分自身の生活を養うこと。また、自分が何を修養すべきかを自身で求めていくこと。養うことの基本は人を当てにしないこと。自分自身を養えずに人を養うことなどできはしない。
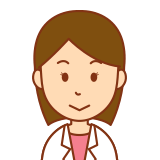
頤はおとがいと読んで、上顎と下顎が向かい合っている象。口の意味。卦の形が、口を開けた形に似ている。口は食物をとりこんで人体を養うから、頤に養の意味が加わる。上下に分けて見ても、上艮は止まる、下震は動く。食べるとき上顎は大体止っていて、下顎が動く。この点でも頤の意味になる。
初九が下顎で、六二・六三が下歯、上九が上顎で、六四・六五が上歯と、口の格好を見て取ったのである。山雷頤の卦は歯の卦だと見ても良い。なぜなら、歯という字の上には、止まるという字(外卦の艮)、その下に二爻から五爻までの四陰の歯牙が並んでいて、下の方から三方を囲っているのが震の初爻の一陽である。
頤の卦は歯であり、顎であるが、ここから食べ物を入れて体を養って行く。それが口の最大の働きである。この働きの意味を推し拡げていくと、徳を養う、人を養うという様に一面において努めることにより、他の一面を大きく裕かに養い育てて行くことになる。
反面、頤の道というのは、一方から一方へと尽くすだけでなく、お互いの身に返って来るのである。体養においても徳養においてもそうである。
貞しければ吉、卦を総括的に断ずることばであるが、内容的には観頤自求ロ実を受けて、それが貞しければ吉。いわば倒置法。
頤を観るとは、問う人が平生何を頤っているかをよく見ること。自ら口実を求む、口実は口を実すもの、自分の口を実そうとする手段を観る。頤を観るの観るは意味上ここまでかかる。
占って頤の卦が出たら、その人貞しければ吉である。その人が、平生何を頤っているか、また自分自身を頤う手段として何をしているかを観察せよ。それらがともに貞しければ、吉である。
彖曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。
彖に曰く、頤貞吉とは、正を養えば吉なり。頤を観るとは、その養うところを観るなり。自ら口実を求むとは、その自ら養うを観るなり。天地は万物を養い、聖人は賢を養って以て万民に及ぼす。頤の時大いなる哉。
前半は卦辞の解釈。天地以下は頤うということを最大限に誇張して、頤の卦の代表する「時」を讃える。解釈の必要はあるまい。
象曰。山下有雷頤。君子以愼言語。節飲食。
象に曰く、山下に雷あるは頤なり。君子以て言語を慎み、飲食を節す。
山の下に雷がある。雷が山の下に震うとき、全山の草木みな芽を出す。頤うと名づけるゆえんである。君子はこの卦に法とって、言語を慎むことで徳を頤い、飲食を節制することで体を頤しなう。言語も飲食も、量と質を考えなくてはならない。暴言は人間関係を損ない、暴飲暴食は健康を損なう。言語・飲食ともに程良く慎み、節することが大切である。
初九。舎爾靈龜。觀我朶頤。凶。 象曰。觀我朶頤。亦不足貴也。
初九は、爾の霊亀を舎てて、我を観て頤を朶る。凶。
象に曰く、我を観て頤を朶る、また貴ぶに足らざるなり。
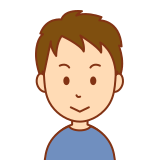
霊亀、亀は将来を予見する神秘的智慧があるのでトに用いられる。亀はまた何日も食わずに生きていられる点でも、この場面に譬喩的に用いられている。朶は木の枝が垂れるのが原義、頤を朶るは、下あごを垂らす、物欲しげに口を開いているさま。爾は初九を指す。我は六四を指す。
初九は陽爻が最下位にある。剛毅で社会の下層にある人。食禄にありつけなくても泰然としていられる筈である。しかるに上位の小人(=陰爻)、六四に「応」じて、心を動かす。あたかも、智慧ある亀を持っていながら、それを捨てて、他人の持っている食物を観て、物欲しそうにぽかんと口を開けている象。智慧の亀を持っていても、この人は、もはや貴ぶに足りない(象伝)。
故に凶という。占ってこの爻を得た人、汝のなかにある智慧を働かそうとしないで、他人の富を羨めば凶。
六二。顚頤。拂經。于丘頤。征凶。 象曰。六二征凶。行失類也。
六二は、顚まに頤わる、経に払れり。丘に于て頤わる、征けば凶。
象に曰く、六二征きて凶なるは、行きて類を失すればなり。
経は常理。払は違。丘は土地の高いところだから、上の位に譬える。六二は陰である。女が独身でいられず、必ず男に従うように、陰は独立できない。必ず陽に従う。六二はそこで、初九の陽に養ってもらおうとする。しかし下位のものに養われるのは順倒している(=顛頤)。常道に違反する(=払経)。さりとて残る陽、上九に養ってもらおうとすれば(=于丘頤)、二と上とは「応」でない。強いて行こうとすれば凶運にあうであろう(=征凶)。人に期待したり、人に養われることを望まない。自立(自律)すること。
象伝、類を失すればなり、初九も上九も、六二の「応」でない、同類でないから行っても無駄である。占ってこの爻を得れば、助けてくれる人はだれもない。行くときは凶。
六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。 象曰。十年勿用。道大悖也。
六三は、頤うに払る。貞なれども凶。十年用うるなかれ。利するところなし。
象に曰く、十年用うるなかれ、道大いに悖れるなり。
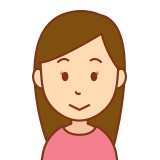
六三は陰柔で「不中」(二でない)、「不正」(陰爻陽位)。しかも動きの極点におる。内卦震は動であり六三は内卦の一番上だから。つまり不正な動きの甚だしいもの、食わんがためにはどんな不正の行動をも辞せないもの、頤うの道に違反している。六二は、頤養の状態ではないという程度だが頤いに払るとなると、もう完全に頤養の道に背いている。頤いかたが間違っている以上、頤うということ自体は正しくても凶である。
占ってこの爻が出たら、事は正しくても結果は凶。十年間動いていけない。何の利もない。
六四。顚頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。 象曰。顚頤之吉。上施光也。
六四は、顚まに頤わるるも吉なり。虎視眈々たり、その欲逐逐たり。咎なし。
象に曰く、顚まに頤わるることの吉なるは、上の施し光いなればなり。
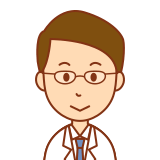
眈々は虎が下をにらむさま。逐々、『釈文』に、敦い、速い、遠いの解が見える。朱子は、飽くことなく次ぎ次ぎに欲求するさま、逐うという語感からの解釈。
六四は陰である。人を養うべき高い地位(上)にあるが、自分を養うこともできない。まして天下を養うことはなおさらである。そこで初九の陽に願いを求める。
上位者が下位者に養ってもらうのは顛倒であるが、六四の場合、六二とちがって、吉である。何となれば、六四と初九は、ともに「正」であって、相い「応」している。
柔順で正しい四が、剛で正しい初に養われるのは寧ろ当然で、しかも、六四が初九に養いを要求するのは、それによって下々の者に広(=光)く施しをしようというのである(象伝)。されば顛倒していても吉なのである。ただし柔弱な上位者が強力な下位者に養いを求めるのである。
上位者が多くの人々を養うために、下位の賢人に自分の足らざる面についての教えを求める。これは上位が下位から逆に養われることである。
ともすれば相手をつけあがらせ、慢られる惧れがある。六四としては、虎が下のほうを睨むように、威あって猛からぬ態度で、初九に接すべきである。また広く施しをするために、初九に養いを要求するのであるから、初九に対する六四の欲求は、虎の飽くなき欲のように、次ぎから次ぎとあとを逐って発せられるのが当然である(=其欲逐々)。そうしなければ下々への施しは続かない。このようにして始めて咎なきを得よう。
自分一人では任務をこなす力がないものの、幸い下の者の力を借りることで、それを全うできる。本来なら、下の者の力を借り(養われ)なくとも任務をまっとうできれば理想だが、それが無理なら力を借りてでも全うすべきである。
占ってこの爻が出た場合、天下を潤すためならば下位の有力者から取り立ててもよい。ただし慢られぬように。そうすれば咎なし。
六五。拂經。居貞吉。不可渉大川。 象曰。居貞之吉。順以從上也。
六五は、経に払れり。貞に居れば吉なり。大川を渉るべからず。
象に曰く、貞に居るの吉なるは、順にして以て上に従えばなり。
六五は陰柔で「不正」(陰爻陽位)な性格であるから、君位にありながら、万民を頤うことができない。そこで位のない実力者、上九の剛に頼って、民を養ってもらおうとする。これは常道に違反している(=払径)。しかし何といっても人を養おうという正しい動機から出た苦肉の策なので、その正しい発意を持続して(=居貞)、すなおに上九に任せ切るならば吉である(象伝)。
占ってこの爻を得たら、他人の力に頼って成功するであろう。相手を信じて静観していれば吉。
上九。由頤。厲吉。利渉大川。 象曰。由頤厲吉。大有慶也。
上九は、由って頤わる。厲くして吉。大川を渉るに利あり。
象に曰く、由って頤わる、厲くして吉、大いに慶びあるなり。
六五の君は、上九の養いによって、万民を養おうとする。天下は上九に由って頤われるのである。上はもともと位のない位置であるが、今や君主の委任を受けて君主の上に位置し、重い責任を負わされている。だから常にその任にそむかぬよう、戒慎恐懼して、始めて吉を得るであろう。
剛毅の性(陽爻)、しかも最上位にある故に、誰に憚ることなく万民救済の手腕を揮い得る。そこで大川の障害をも渉り切ることができる。
占ってこの爻が出たら、人に代わって大任を引き受けることがある。よく戒慎すれば吉。危険をも乗り切れる。象伝の慶は福と同じ。



コメント