澤雷随(したがう・したがわす/時に従い、人に従う・随喜)
reliance:依頼
following:随員,随行者;家来,従者,配下,子分;信奉者,崇拝者;愛読者;ひいき
時流に乗ぜよ。人の言葉に耳を貸せ。
我誠意を尽くせば、彼もまた我に応ずるべし。
豫必有隨。故受之以隨。
豫べば必ず随うことあり。故にこれを受くるに随を以てす。
悦び楽しめば、必ず多くの者がそれに付き従ってくる。
従うべきものはいろいろあるが、何に従うべきなのかを見極めることが重要である。
随喜:人の喜びに随したがって喜ぶ
他人が善いことをするのをみて、これに従い、喜ぶこと。『法華経』では、この経を聞いて随喜し、教えを伝える功徳を力説し、『大智度論』では、善を行った本人より、それを随喜した者のほうの功徳がまさっていると説いている。天台宗では滅罪の修行として懺悔する五悔の一つに数える。転じて、仏教の儀式に参列することをいう。さらに大喜びすることをいい、「随喜の涙を流す」などと用いられる。[石上善應]
[出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)]随喜功徳とは人が喜んでいるときに同じ気持ちになって心の底から喜んであげること。
これが功徳(徳を積むこと、徳積み)になる。
時として我々は人の成功や、人の幸福を素直に喜べないことがある。
だが、他人の善きことを妬む心は醜い。
人の懐を斟酌なく責める姿勢はさもしい。
現代人は「分を知り、足るを知る」という奥ゆかしさが少なくなってしまった。
人と比較せず自らの道を往き人の喜びを、心から我が喜びとする毎日が徳積みの修行。
[出典:https://blog.buddha-osie.com/kotoba/1105/]
何事も時に従い、人に従って行くのがこの卦の出たときで、自分の力でやれるからとやせ我慢をせず、ここは他力本願とばかり人の力を借りたほうが良いときでもある。だから、人の力の借りれる時は決して運勢の悪いときではなく、むしろ上り坂と云ってよい。
どんなことも実行に移してよいが、ただ一つ単独では決して功を奏せず、所詮は一人相撲の終わることになる。
必ず仲に入ってくれる人が必要で、それは先輩、後輩、知人、身内を問わず、多少なりとも骨を折ってくれる人が要求される。
又、不思議とこの卦のときは誰か役に立つ人のいるときで、その人に依頼するのが嫌な場合でも頼めば力になってくれるし、その方がうまく行くようになるものである。
[嶋謙州]
ゆとりができると、人々が魅力を感じてつき随ってくる。人ばかりではなく天下の万物、金まで付き随ってします。これが随であります。
この時に大事なことは、いい気になって共に遊んでおってはいけません。
時がくれば退いて有益な書物を読んで自分を修めなければなりません。
でないと、とんだ問題が生じやすい。そこで易経も次の蠱の卦を配しております。
[安岡正篤]
隨。元亨利貞。无咎。
随は、元いに亨る貞しきに利あり。咎なし。
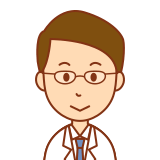
序卦伝に、民を悦ばせしませるならば、ものみなこれに随う、悦び楽しむものを持っていれば誰でも従いやすい、そういった自然な人情から、豫卦のあとに随卦がくる、という。随は従うの意味。総じてこの卦は、人を従わせる道それはこれを捨てて人に従うことでもある。
随は、卦変でいえば、困䷮の九二が初六と入れかわった形、または噬嗑䷔の上九が六五と入れかわった形。また未済䷿の九二が初六と、上九が六五と入れかわった形でもある。いずれも剛が降りて来て、柔爻の下に従うのだから、随と名づける。また上下に分けて見れば、下卦は震、動く。上卦は兌、説ぶ。こちらが動いてゆき、むこうが説ぶので、随の意味になる。
豫の時には、地上に奮い出ていた震が、隨の時には兌の下にある。兌の方位は西、季節は秋で、陽気衰え潜む時である。故に、秋になり今まで奮動していた雷気が隠れ、他日また奮い出る為の用意をしている。豫とは真逆の象意となるのである。
豫は順をもって動き時に従って雷気発動したのと同様、隋も時に従って雷気が隠れるもの、どちらも時に従って動くことには変わりがない。だから時を非常に重要視している。
隨は、時を得れば万物を鼓動させる雷気が、兌の下に隠れ時の来るのを待っているのであり、時が巡り来れば地上、天上に現れて万物を振興させる。勢い盛んなるものが時に従い、内に実力を潜めつつ、兌の力の弱い者の下に従い付いているのだから、これもまた大いに亨るわけである。
九五の君は剛をもって位正しく中している。六二もまた陰爻陰位にいる柔中。よく君に応じている。人君なるものが善なる道、義なるところに正しく従い付いて行く時は、臣下たる者もまた、君主の命を奉じて事に従い、全ての者が位正しく従って行くのである。
そのように隨の道は、ものを明らかに見て、貞しく理解し、盲従ではなく、正しく時義に適うようにしてゆくのである。正に適えば、大いに亨って咎もないわけである。
大体、自分が虚心に他者に随えば、他者もまた自分に随って来るものである。相互に随うということになれば、当然何事も通る。そこで判断として、元いに亨るという。けれども貞しきに利ありで、美しいことを条件とする。また、貞しくてこそ咎なしである。随うことが貞しくなければ、望むこと元いに残っても、咎を免れない。
彖曰。隨。剛來而下柔。動而説隨。大亨貞无咎。而天下隨之隨之時義大矣哉。
彖に曰く。随は、剛来たって柔に下る。動いて説ぶは随なり。大いに亨る貞にして咎なし。而して天下之に随う。随の時義大いなるかな。
時義は、時と意義。六十四卦は世界の間断なき転変のうちの、ある時間、ある様相を、切断面として示している。だから各卦にそれぞれ時と意義がある。
象曰。澤中有雷隨。君子以嚮晦入宴息。
象に曰く。沢中に雷あるは随なり。君子以て晦きに嚮って入りて宴息す。
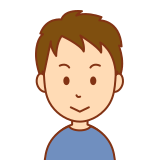
晦は日暮れ。雷が沢の中にあるというのは、活動期以外には地底深く蔵れ伏しているのである。雷が時に随って休むので随と名づける。君子はこの卦に法とって、昼は休まず働くけれど、日の暮れにむかえば、奥に入って安息する。
時に随うとは、自然の時の流れ逆らわないこと。勢いが弱まった時に事を強引に進めてもうまく運ばない。時に随えば時を味方にでき、いずれ時を用いることが出来るようになるのである。
初九。官有渝。貞吉。出門交有功。 象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。
初九は、官渝ることあり。貞なれば吉。門を出でて交わるに功あり。
象に曰く、官渝ることあり、正に従えば吉なり。門を出でて交わるに功あり、失あらざるなり。
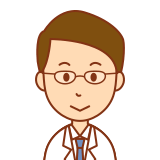
同じく随うといっても、卦辞は他者が自分に随うことを問題とし、爻辞は自分が他者に随とを問題とする。初九は下卦の主人である(すべて一陽二陰の卦では一陽が主、二陽一陰の卦では一陰が主)。震は動く意味で、動いてこそ随うの意味も出て来る。つまり初九は人に随おうとする。随には、したがう、しなう、の意味がある。しなうとは竹がしなるように、柔軟に身を屈すること。地位や立場、功績、過去の栄光などにしがみつかず、一旦死んだつもりになって自己を抑制する。しっかりした自分軸を持ちながらその上で己を捨てる。
他人に随えばそれにひきずられて、いままで守っていた主義を変えることにもなる。たとえば職掌を変えるようなもの~官渝ることありである。ただ変るにしても、正しい道に沿って変わるのならば吉である。また、自分の門から出て、赤の他人と交際すれば良い効果がある。人の情として、妻子の言うことは、誤っていても従い、嫌いな他人の言は、薄くても悪いとするのが常である。門を出て、随う対象を広くすれば、そうした過失はない(象伝)。
これはそのまま占う人への戒めである。占ってこの爻を得れば、官職の変動があろうが、正道を守っていれば吉。進んで他人と交際すれば効果があがるであろう。
六二。係小子。失丈夫。 象曰。係小子。弗兼與也。
六二は、小子に係りて、丈夫を失う。
象に曰く、小子に係る、兼ねて与せざるなり。
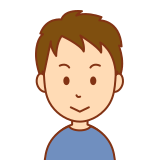
小子は若者。孔子が弟子をよぶ二人称に小子を用い、名詞としても「わが党の小子」などということ、『論語』に見える。丈夫はもと、身長一丈の男。子供に対しておとなを意味する。
卦の解釈として、小子は小人物で初九のこと。丈夫は立派な人で九五のこと。
この六二は、初九の比爻であり九五の応爻で、自分の従おうとする対象が初九と九五の二つある。
水雷屯の六二同様、そのどちらに従うべきか迷う。澤雷随の六二は正応の五爻とは遠く離れていることから、成卦主爻である身近な初九に惹かれ、本来の正しい相手に応ずることができないのである。
大体、人に随うという場合、とかく近いものに随いやすい。六二は心弱く(陰爻だから)、操を守って正当の配偶(九五)を待つことができず、初九に随って、九五の正しい「応」をなくしてしまう。
主ある婦人が、若い男友達にひっかかって、りっぱな夫をなくしてしまう象である。あるいは吝といわないが、わるいことは明らかである。
象伝の意味は、小子に係れば、丈夫を失うので、両手に花ということはできない。占う人、目前の小利に釣られて、本分を見失うことがある。心すべきである。
六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。 象曰。係丈夫。志舍下也。
六三は、丈夫に係りて、小子を失う。随って求むるあれば得。貞に居るに利あり。
象に曰く、丈夫に係るは、志し下を舎つるなり。
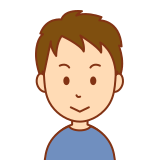
丈夫はこの場合、九四を指す。小子は初九。陽の上位にあるほうが丈夫、下位のが小子である。大体、陰はひとり立ちできないもの。六三の陰も上に「応」がない(三は上と応ずべきだが、ともに陰で応じない)ので、身近い九四の陽にかかる。下にも初九という陽がおるにはおったが、九四にかかることで、初九を自分から捨ててしまう(象伝)。ちょうど、夫のない婦人が、りっぱな壮年の男に心惹かれて(=係丈夫)、若い男友達を失う(=失小子)という象である。九四は陽剛、大臣として実権を握っている(五が君位、四は君のすぐ下)。この頼もしい男に、六三は随っている。欲しいものがあれば何でも与えてくれる(=随有求得)。六二とちがい、自分より優れた相手に随う点で、よろしきを得ているが、九四は正当の「応」ではない。
不正な意図で道ならぬ相手に媚びているという嫌疑を免れがたい。だからあくまで貞しい道に居るように心掛けねばいけない(=利居貞)。この爻を得た人、有力者に随えば利得があろう。ただ不正な動機からしてはならない。
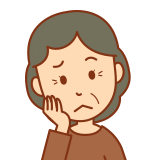
六二の場合と同じく、丈夫=九五、小子=初九だが、この六三は六二と反対に、丈夫に係わって小子を失うのである。
この卦は隨の時で、陰爻はみな陽爻に従う意味を見ているのだが、成卦主の初九も定卦主の九五も、この爻とは応比になっていない。そこで従うことを自ら進み求めて、その相手を得なくてはならないのだが、いずれか一方に従う相手を定めるとすれば九五の君に従うのが当然である。そのため下にいる初九を失うことになるのである。九五の丈夫に心を寄せて初九の小子を見捨てるといったところである。
それは自然の成り行きでそうなるのではなく、初九も九五も共に応比でないから、いつまでも相手から手を差し伸べてはくれない。
そこでこちらから一方の爻を求めていくわけだから隨の徳を持つ九五に従うべきなのである。こちらから進んで求めて行って、初めて丈夫に従うことができるという条件付きとなる。
九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明。何咎。 象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。
九四は、随いて獲るあり。貞なれども凶。孚あって道に在り、以て明らかなれば、何の咎あらん。
象に曰く、随いて獲るあり、その義凶なり。孚あって道に在るは、明の功なり。
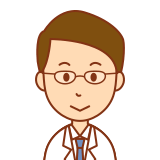
九四は剛毅な性格(陽爻)をもって、五の君のすぐ下に位置している。その実力は君とひとしい。人民は九四の宰相を通じて間接的に君に従うようになるため、直接的には九四に従い集まってくるのである。このような力をもちながら君に随うのであるから、望むものすべて得られるであろう。故に占断の辞として、随って獲るありという。けれども九四の威勢は、すでに五の君をしのいでいる。疑われること、避けがたい。されば、その行為は貞しくても凶である。ただ心に誠あって道に外れず、しかも明哲保身を忘れなければ、ついには君も安心するし、下の者も心から服従するであろう。民が自分に集まってきたとしても、本人が自らの分限立場を弁え驕らず努め公明正大ならば、何の咎めも受けない。こうなれば何もない。占ってこのを得た人が、政治の重任に当たる場合、この戒めを噛みしめるべきである。象伝、あとの句の意味はありて道に在れば何のあらん、明哲保身のおかげである。
九五。孚于嘉。吉。 象曰。孚于嘉吉。位正中也。
九五は、嘉に孚あり、吉なり。
象に曰く、嘉に孚あり吉なるは、位正中なればなり。
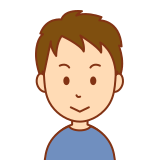
嘉は善。孚は信、約束を守る。九五は陽、陽は善である。「正」(陽爻陽位)であり「中」(五は外卦の中)である。九五は下卦の六二と「応」の関係にあるが、六二もまた「正」(陰爻陰位)で「中」(二は内卦の中)。中正は嘉きもの。中正が中正に「応」ずるということは、嘉きものとの約束に忠実であるということ。されば、嘉に孚ありという。占ってこの爻を得た人、善き友と結束すれば、結果の吉であること、いうまでもない。
上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。 象曰。拘係之。上窮也。
上六は、これを拘え係る。乃ち従ってこれを維ぐ。王用て西山に亨す。
象に曰く、これを拘え係る、上窮まるなり。
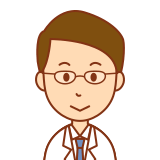
上六は陰爻、人に随うもの。しかも随の極点におる。人に随うことがその極に達すると、相手に縛りつけられて、離れられないようになる。辞はそれを象徴する。「これ」は上六自身を指す。とらえられ縛られ、そのうえ(=乃)重ねて(=従)太い綱で柱に繋がれる。
表現は悪い意味のようだが、そうでなく、然るべき人に随う場合、これほど固く結ばれるべきだというのである。これは随うことの極であって、万民が君主に心服していて君主の傍らから動こうともしない。その様子がまるで杭か何かへ綱でしばってあるというような表現なのである。
このような、随うの誠意があれば、神明にも通ずる。まして相手が人間ならば通ぜずにはいない。その道理を、作者は、王用て西山に亨すという句で象徴的に示している。西山は岐山、周の西にあるから西山という。亨は享と同じ祭る意(大有九三参照)
王者は誠をもって西山に祭る故に、その誠は西山の神に通ずる。人に対してはなおさらのことである。山や川を祭るについて占って、この爻が出たら、誠を以て祭れば吉、という答えになる。象伝の上窮まるとは、随の道が上に極まったこと。



コメント