水天需(躊躇・期待/進んで行くために時を待つ)
wait,waiting:待機,待つ
時機の到来を待つべし。ただし、将来に備えて英気を養うべし。
機はまさに熟さんとす。望みを捨てず忍耐を持って努力すべし。
物穉不可不養也。故受之以需。需者飮食之道也。
物穉ければ養わざるべからず。故にこれを受けるに需を以てす。需とは飲食の道なり。
ここでの需の意は、養われることを「需つ」「待つ」「もとめる」こと。
飲食の道とは、人を養うことで、飲食に代表させている。
待つこと、待機の姿勢、これがこの卦のすべてである。
運勢は決して悪くはなく、徐々に好転し上昇ムードにある。しかし、今は動いてはいけない。動けばとんでもないことになり、相手の術中に陥ったり人に騙されたりする。物事は不成立に終わるし、実行に移したことは思うように行かない。
人間はとかく辛抱が肝心なのは言うまでもないが、えてしてこらえ切れなくなって動き、失敗するケースが多いものだ。
待っていれば必ず物事が自然と動いてくる。その時が勝負。それまで悠々と余裕を持って準備を整えておくこと。前途は有望、今しばしの辛抱である。待つこと。時節の到来まで待とう。
[嶋謙州]
子供が成長すると、内在しておった人間性の要求が発達してきます。
つまりいろいろの要求を持つようになる。これが需(もとむ)であります。
[安岡正篤]
需という字は「待つ」という意味である。古い本には「密雲雨ふらずの象、雪中梅ほころぶの意」と書いてある。デューマの傑作「モンテクリスト」の最後の言葉を借りるなら「待て、しかして希望せよ」という状態なのだ。この説明に、「孚あれば、光亨る。貞吉。大川を渉るに利し」と書いてあるのは、正しくモンテクリストである。
[高木彬光/易の効用]
需有孚。光亨。貞吉。利渉大川。
需は孚あれば、光いに亨る、貞なれば吉なり。大川を渉るに利あり。
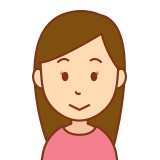
水天需の時は、待てば必ず来るというのがポイント。ただし、焦ったり、むやみに動いてはならない。静観しつつ、日々精進を怠らない。すなわち、水天需の時は心と体にたっぷりと栄養を摂らせて、将来、大川を渡る一大イベントための準備をする時。各爻では、いかに待つべきか場面に応じて解説されている。
孚があれば(虚心で打算のない鳥が卵を孵すような心情)最後は大いに亨るであろう。さらに正道を固守するならば(=貞)、吉であり大川を渡ることもできるであろう。
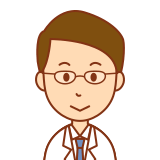
『需』という字は、冠は雲の略字で雨、下の而は天の象形。内卦が乾、外卦が坎のこの卦をそのままに表した天の上に雲が上っている形。
『需』は『まつ』という意味だが、『需つ』と『待つ』とでは心理的な点で大きく異なる。『待』は消極的・受け身、期して待っているような状態(相対的関係)だが、『需』のほうは時間的な意味を主とし積極的に求めつつ控えているような、出動命令があるまで待機しているような状態。時が来れば直ちに立ち向かおうとする力を内に蓄えている。
屯は困難を前にした青年の苦しみであり、需は老練家の待機姿勢を表しておる。この卦が、なぜ山水蒙のすぐ後に配置されているかと言えば、需の卦は物を養育するのに最も大事な『飲食の道』を説いたものであるから、陰陽交わって難みの中に生れ出た童蒙が、求め待つのは言うまでもなく飲食による養いなのである。
需のときは、需つべきである。需つべき時に、かたく守って需てば、やがて坎の難みが解け、大いに亨り得るものである。
この時期に処するには、孚の心が何よりも重要。この『光いに亨る』というのも、直ちに亨るのではなく、時が来るのを動かず固く守っていることが条件となる。この坎険の解けるのを需って後に亨るのである。
乾の剛健で、坎険のなくなった川を安心立命の心持ちで渡っていくように、容易に大事が成就するのである。
彖曰。需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利渉大川。往有功也。
彖に曰く、需は須なり。険前に在るなり。剛健にして陥らず。その義困窮せず。需は孚あれば、光いに亨る、貞なれば吉、天位に位す。正中なるを以てなり。大川を渉るに利ありとは、往けば功あるなり。
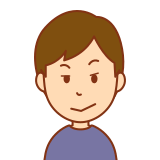
需は「待つ」という意味。前方に険阻があるから、待つ。乾☰は剛健で本来進んでやまぬものであるのに、よく時を待ち険に陥らないでいる。この主義でいけば困窮するはずはない。
需は、孚有れば、光いに亨る。貞しければ吉とは、九五がその剛くまことある徳で、至高の位におるからである。九五も九二も『正』で『中』であるからである。大川を渉るに利ありというのは、待ってから往けば成功するということである。
象曰。雲上於天需。君子以飲食宴樂。
象に曰く、雲、天に上るは需なり。君子以て飲食宴楽す。
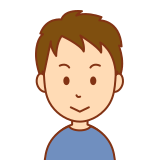
天空に雲が広がり、待ち望んでいた雨がもうすぐ降りそうだ。その間、ただ酒や食に耽るのではなく、楽しみながら余裕を持って待つことが大切だ。
そのためには、リーダーとしての役割は常に需要に応じて備えておくことが必要だ。景気の悪化や干ばつの際でも、十分な備蓄を持っていれば、飲食に困ることなく状況の変化を待つことができる。
初九。需于郊。利用恆。无咎。 象曰。需于郊。不犯難行也。利用恆。无咎。未失常也。
初九は、郊に需つ。恒を用うるに利あり。咎なし。
象に曰く、郊に需つは、難を犯して行かざるなり。恒を用うるに利あり、咎なしとは、いまだ常を失わざるなり。

需つというのは、前に険☵があるからである。初九は上卦の険☵に最も遠い。だから郊で需つという。郊とは都の外、遠い場所のたとえ。また初九は陽爻、剛毅であり、その常の居場所を失わないでいることができる。占ってこの爻を得た人、このように遠くで需ち、常を守るならば、咎はない。
郊とは、郊外などという言葉もあるとおり、偏鄙な土地で、たとえば洪水のある河からいくらか離れたところに逗留して、水のひくのを待っているような感じである。むかしの日本でも、たとえば大井川とか、天竜川とかが降雨のために水かさが増すと、川どめになって、旅人が両岸の宿場で足どめにされることがよくあった。
それと同じような状態だが、これが何日も続くと人間はどうしても退屈して来る。日本の場合、そういうカモをねらって、賭碁や賭将棋などで、懐の金塊をまきあげようとした人間もよくいたらしい。災難はいま直接身にせまるというわけではないが、こういう形で、別の思いがけない災にぶつかることもあるのだから、十分注意して、普段どおりの生活を続けていけという教えである。
[高木彬光/易の効用]
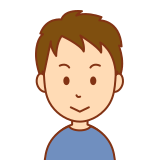
『郊』は郊外、『坎険から遠く離れているところ』という意味で用いられ、外卦の坎険に近いか遠いかを主として爻の安危を見ている。
初爻は、人体でいえば足。事については始め。強弱で言えば弱。
乾の剛健なる中にあっても進むという気運もまだ兆しの程度。過不足からすれば不足で、需つべき時にあってあえて険を冒さない。状況が変化するまで、そのまま動かずにいることが一番。『恒を用いるに利ろし』は、事を控え変動を求めず日常の慣習を継続していれば良いということ。変ずれば水風井となる。
井戸は所有者が変わってもそのまま変わらないから、新たな所有者に対しても役に立つ、恒を失わないのを尊いことだとする。
『咎なし』とあるのは、本来なら咎あるべきだが……という意味で付け加えられており、初爻で力が弱いものの、陽位に陽でおるので、需の時において軽進する恐れがないわけでもない。
九二。需于沙。小有言。終吉。 象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。
九二は、沙に需つ。小しく言うことあり。終に吉なり。
象に曰く、沙に需つは、衍にして中に在るなり。小しく言うことありといえども、吉を以て終るなり。
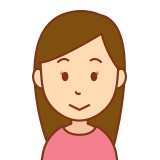
九二は初九に比べて☵に近い。☵は水。水に近いから沙という。九二が沙浜において待っているというのは、九二は剛にして中を得ており、心がひろくゆるやかに、ゆったりとして、中庸の徳を自分の居場所としておるのである。初九にくらべれば、険難の地にやや近くして、多少の非難を受けることはあるけれども、ついには、吉を得る。
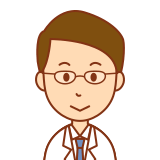
『沙』は水辺・川辺のこと。初爻を郊外とし、堤防の外と見れば、沙は砂地。
二爻は、初爻より少し、危険・困難に近い位置にいる。先に危険や困難(川を危険と見る)があり状況の変化を待っている。それを「川の手前の砂地」と表現している。
『言』は、言葉ではなく、障り・傷などを意味する。何か出来事があるために苦しみの言葉を吐いたり、批難の声を聞いたりする……その両方に通じる意味の字。何か出来事があるために苦しみの言葉を吐いたり、批難の声を聞いたりする……その両方に通じる意味の字。
沙とはいくらか水に近い地だが、三爻の「泥」と違って、まだ水際というほどではない。それでも、いくらか危険に近づいたのだから、多少の難はまぬがれない。例えば川越人足に物言いをつけられたようなもので、それが「少しく言有り」だが、自分を固く守って動じなければ、そういう小難はすぐ去ってしまうということである。
[高木彬光/易の効用]
九三。需于泥。致冦至。 象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬愼不敗也。
九三は、泥に需つ。寇の至るを致す。
象に曰く、泥に需つは、災い外に在るなり。我より寇を致す、敬慎すれば敗れざるなり。
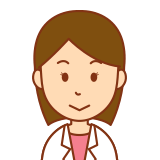
九三は水☵に接した場所だから泥という。九三は険☵に間近く進んで、今にも険に陥ろうとしている。泥のところで待つようなもの。剛爻が三つも重なっては剛に過ぎ、しかも「不中」(二が中)である。災害の程度は叱言ですまない。外敵の攻めてくる事態を招くであろう。外卦☵に災いの因がある。外敵は、九三が妄進することで自ら招いた。だからよく敬み慎んで進むならば、失敗することはない。
これはいよいよ水際で、身が危くなった状態なのだ。危険を悟らず進みすぎ、泥の中へ足を踏み込んで、抜き差しならなくなった形と解釈してよい。情熱がその方向なりタイミングを誤ったのである。戦争ならばこういうときにたたかれては、こっちの応戦ができないのだから、敗北は必然の運命である。とにかく、安全な場所まで戻って、体制をかためなおす心得が必要なのだ。
[高木彬光/易の効用]
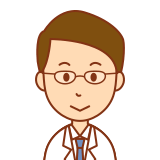
三爻は二爻よりも一段と坎険に近づき、坎険と接している位置にあり、非常に危険な一歩でもずぶずぶと足が沈んでしまう泥濘のような場所にいるそれで一歩でも進めば坎中に陥って傷害を受ける。『冦の至るを致す』というのが動いて自ら冦を招くこと。
動かずにおれば大丈夫だが、三爻は乾の極まるところ、三陽の中でも最も進む勢いが激しいから、前に進みたくて、動きたくてしようがない。よほど注意しなくてはならない。
このような時は、乾為天の三爻『君子終日乾乾。夕べまで愓若たれば厲うけれど咎なし』の戒めが必要。坎険は自分の中にあるのではなく外にあるのだから、自分から進みさえしなければ危害は受けずに済むのである。
六四。需于血。出自穴。 象曰。需于血。順以聽也。
六四は、血に需つ。穴より出づ。
象に曰く、血に需つは、順にして以て聴うなり。
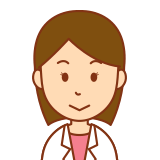
四はすでに☵のなかに入りこんだ。☵は険である。殺傷の場所の血溜まりに足をふみこんで需っている象。しかし六四は柔であり、「正」を得ている(陰爻陰位)。おとなしく需って、それ以上進もうとはしない。だからやがてはおとし穴から這い出ることができよう。象伝の意味は、血だまりのなかに需ちながらも、柔順に時運に従(=聴)っていれば、やがて穴から出られるということ。筮してこの爻が出たら、傷つくようなはめに陥るが、最後には抜け出すことができる、という判断になる。
泥の中でもがいているところを敵に襲われ、切りつけられて散々に出血し、穴の中に逃げ込んで、辛うじて命だけはとりとめたという状態である。あわてて飛び出すと、今度は命とりになるが、じっと時を待っていれば、救いの手が伸びてきて、九死の危地から逃れられるという意味なのだ。
石橋山の合戦で大敗した源頼朝が大木の空洞の中に逃げ込んで、平家の捜索隊を迎えたようなもので、運を天にまかせてじっとしていたために、梶原景時苦心の腹芸に救われたようなものである。
[高木彬光/易の効用]
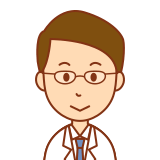
卦の『需つ』ということを主軸にし、各爻の陰陽と位置とによって上手く需つことが出来るかどうかを見ていくと、この爻は坎の中の一爻であるから、進んで険中に陥り救いを求めているような状況。
『血に需つ』というのが、もう既に坎の中に陥って傷ついており、ズタボロの状態で需っている(坎は血の象)。
『穴より出ず』は、やがて内卦の三陽爻が進んできて救い出してくれるので坎険を脱出できる。
陰位に陰でいるこの爻は、内卦三陽の進んでくるのに聴従し、それに付いて穴から救出されるということ。
九五。需于酒食。貞吉。 象曰。酒食貞吉。以中正也。
九五は、酒食に需つ。貞なれば吉。
象に曰く、酒食の貞吉は、中正なるを以てなり。
酒を飲み食べ物を食べて、からだを養い、心を養っており、時期が至ってそれが自然に服従して来るのを待っておるのである。優遊自適して、無為にして天下を治める。
易経にはよく「貞吉」という言葉が出てくるが、これは「自分の本分を守って動かなければ吉」という意味に解釈していいだろう。
これは、勢いのほうからいうなら、一応自前のの危機を脱して一息ついた形なのだ。部下にも酒食を与え、自分も宴に加わって、労をねぎらっているような状態である。
例えば、源頼朝が石橋山から海路、下総の国まで逃れて、やれやれと一息つきながら、再挙の方針を心中に練っているような状態である。
「用心棒」という映画でいうなら、主人公椿三十郎が、お堂の中で出刃打ちの稽古をしているようなもので、積極的に出ていくには、まだまだ気運が熟さないのである。
[高木彬光/易の効用]
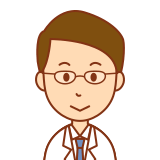
五爻は成卦主爻。
思慮深く急功を求めず、尊位にあって剛健、悠々と構えて時を需つ爻である。
同じ外卦の坎でありながら、坎の象を血とも水とも穴とも見ず『酒食』とするのは、この卦が飲食の卦でそれを司るのがこの爻だからである。
腹膨れれば心緩むというように、往々にして逸楽に陥りやすい。そこで『貞吉』という言葉が出てくる。
ただし、五爻は君位にあるのだから、自分が酒食に耽っているのではなく、臣や家来などに酒食の道を与え、大いに余力を蓄積させておき、一朝有事の際に用いるのだと教えているのである。
上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。 象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。
上六は、穴に入る。速かざるの客三人あって来る。これを敬むときは終に吉なり。
象に曰く、速かざるの客の来る、これを敬むときは終には吉とは、位に当たらずといえども、いまだ大いに失せざればなり。
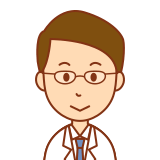
「速」は待つ。したがって「不速」は待たない、すなわち「不速」は思いがけないの意味。
「速かざるの客」は「招かざる客」と同義であり、現代では不快な客人を表す言葉として使われていますが、本来は予期しない助けをもたらす人を指していました。
困難に陥ると、人は頑なになり、救済を拒絶することがあります。しかし、本当に困った時に現れた救いの手を追い払ったり、逃げたりすることをせず素直に受け入れなければならないことを教えています。
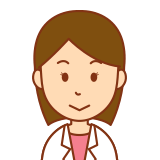
上爻は、四爻と同じ坎の陰爻で穴の象がある。
四爻には『穴を出ず』とあり、上爻は『穴に入る』とあるが、この爻は外卦の終わりに居て出て行くところがないから、穴に入るとある。
『速かざるの客』は内卦の三陽爻を指す。
「速く」は「招く」と違い「需」の意味を持つ。速かざるとは需たない、つまり期待していないということである。内卦の三陽爻は呼べばやってくる、呼ばなければやってこない、というのではなく、需つべき時に需って、進むべき時が来たから進んでくる。今まで下にあって待機していた内卦の三賢人が進むべき時を察して上り進んでくる。この上爻は陰で柔順だから、三陽爻の進んでくるのを拒むことなく敬いもてなして、吉を得るというのですある。
それをもてなすのは本来君位にある酒食貞吉の五爻だが、需の卦の終わるところは上爻で、この時に進んでくるので、この上爻が代わってもてなす。
もてなすべき位ではないのだが、陰位におる陰爻であるから、進んでくる強剛なもの(内卦の乾)には反発することがないから、大きな失態がなくて済むのである。
一難去ってまた一難、一度逃れたはずの穴にもう一度落ちたところへ、来てもらいたくない借金取りのような相手が三人もそろってやって来たという感じである。何が何でもあやまり奉って、危険をのがれるほかはないだろう。こんな状態では、一人とケンカしても負けるのが当たりまえなのに、まして三人も向こうにまわして勝てるものか。
大変乱暴な表現のようだが、私は易経を読んで、この部分に来ると、自然に涙が出てくる。明治の易聖といわれた、呑象、高島嘉右衛門の娘は、明治の元勲、伊藤博文の息子と結婚していた。そして、日清戦争当時の総理大臣は、この伊藤博文だった。歴史的大政治家である博文は、大東亜戦争当時の白痴的指導者たちとは、ぜんぜん人物の大きさが違っていて、開戦当時から、どうして戦争を終結すべきかという大問題には、日夜心胆をくだいていたのだった。こういう関係から高島嘉右衛門の彼のブレイン・トラストの一員となっていたのだが、この戦争の終戦当時、嘉右衛門が、日本の前途を占って得たといわれる歴史的占断が、実にこの卦だったのだ。
伊藤首相の危惧はたちまち事実となった。独露仏三国が今まで隠していた牙をあらわして、日本に強圧を加えてきた。いわゆる「三国干渉」の国家的危機が到来したのである。
伊藤博文は、この卦の啓示に基づいて、たちまち人が変わったような軟弱政策に転向した。
講和条件では、最大限の譲歩を行い、最初は日本のものになるはずだった遼東半島、大連、旅順を露西亜の永久的な租借地とされることにさえ、あえて眼をとじたのである。
「隠忍自重、臥薪嘗胆」
これは、彼がそのとき、全国民に与えたスローガンだが、この十年の自重が、日露戦争の大戦果を生ずるようになったのだ。
そして、日本海海戦で、彼が元老として、終戦の大英断を下したのも、政治家としては実に優れた大局観である。その時の講和条件も、当時は軟弱の極と国民に罵倒された。
だが、その判断の正しかったことは、歴史によって証明された。彼はその後、ハルビン駅頭において暗殺されるまで、日本を絶えず最善の方向へリードし続けたのである。
これを国家の柱石といわずに何というだろう。彼の眼中にあるものは、百万人の反対者ではなく、ただ国家そのものだった。そして、博文にこのような最善の道を選ばせた理由の一つが、易聖といわれた高島嘉右衛門の数々の名占だったことは、二人の関係を考えるなら、誰にも否定できないだろう。
私はあえて繰り返す。太平洋戦争開戦当時の指導者たちは、どうしても高島嘉右衛門とはいわないまでも、伊藤博文、三国干渉当時の史実を心に思い起こさなかったのだろう。
当時、東条英機という日本近代史最悪の首相が、陸相時代、日米交渉反対の理由として掲げた口実は、自分はこの条件を呑むようでは、軍の統制に自信が持てない……という強迫的な言葉であった。これを伊藤博文が、日露の講和条約に出発する外相、小村寿太郎に呈した言葉と比べてみよう。「君を今日、万歳の声とともに、送り出す民衆は、おそらく君の帰朝の日、石を投げてこれを迎えるだろう。あるいはさらに、それ以上の暴挙に出ないともかぎらない。その際、僕と桂君(日露戦争当時の首相、桂太郎公爵)は、君の両脇に坐して、君の身を護ろう」
もし、昭和16年当時、日本が米英の強硬政策に屈服したとしよう。あるいは最悪の場合には、2.26事件のように、血なまぐさい内乱的な事件が勃発したかもしれない。
だが、その犠牲は、数十人か数百人か、おそらく万に達しなかっただろう。いわゆる支那事変の犠牲者二十数万にこれを加えても、数字にそれほどの差が現れたとは考えられない。それに対して、太平洋戦争による日本人の犠牲者は、軍人軍属だけでも二百数十万である。領土の喪失はいうまでもない。本土さえ大半は焼土と化し、全国民は死ぬような苦しみを味わった。
この二つの歴史的事実を、じっくりと吟味なさるなら、三千年の長い間、中国において「易は王道なり、帝王の学なり」といわれて尊ばれた来た所以も、おそらく納得されるのではないだろうか。
[高木彬光/易の効用]



コメント